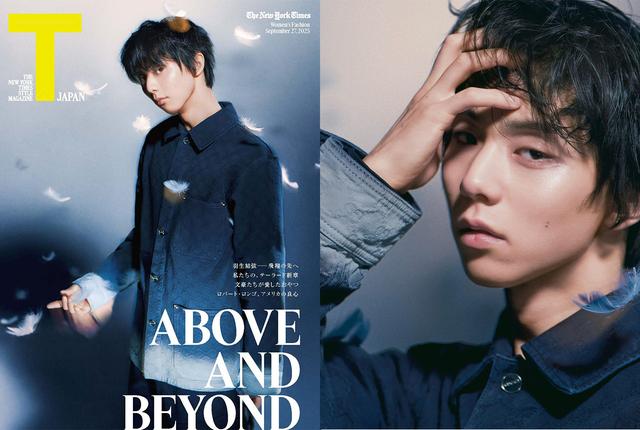BY NICK HARAMIS, PHOTOGRAPHS BY ALLEGRA MARTIN, TRANSLATED BY YUMIKO UEHARA

ニコラス・ワード=ジャクソンのベネチアの家の寝室。壁にはピエトロ・ロンギ派の絵画。アンティークの暖炉の横には、1950年代のイタリア製フロアランプ。
10年ほど前のある朝、ニコラス・ワード=ジャクソンはベネチアを離れようと思い立った。美術商を営むイギリス人の彼と、心理療法士でイタリア人の妻マルゲリータにとって、当時の住まいは5年くらい前から手狭で、観光客の多さにも辟易していたのだ。そこを引き払ってロンドンに戻ると決めたのだが、引っ越し前日、現在は80代になるワード=ジャクソンのもとに一本の電話があった。不動産仲介業をしている妻のいとこが、近所のドルソドゥロ地区にある物件を紹介したいという。サンマルコ広場から運河を挟み、喧騒から隔てられた閑静な住宅街だ。しぶしぶ内見に行ってみると、物件は17世紀に建てられた邸宅2階のピアノ・ノビーレ(註:建物のメインフロア)だった。広さは325㎡ほどで、ホールの片側に寝室が3つ、反対側に書斎とキッチンがある。「ひどくみすぼらしい」空間だったが、足を踏み入れると妙になじみ深く感じられることに、衝撃を受けた。しかも帰り際に出くわした老婦人から「あらニコラス、お久しぶりね」と声をかけられた。「昔のおうちに戻ってくるの?」
驚いたことに、そこは彼が10代を過ごした場所だった。父方の一族は南アフリカの通信社の共同経営者で、父ウィリアムは出張が多かった。父の長期海外出張中に母キャサリンがまさにこのアパートメントを借りて、子どもたち(彼と弟2人)と暮らしていたのだ。場所は覚えていなかったが、印象は記憶に残っていたに違いない。彼は成人後、美術蒐集家となった。主な蒐集対象は18世紀にベネチア近郊で活躍した芸術家たちの作品だ。イギリス人映画監督デレク・ジャーマン(1994年没)による1986年の映画『カラヴァッジオ』では、ワード=ジャクソンが製作をすすめ、脚本執筆にも参加し、17世紀バロック期の画家の生涯を描いている。内見先のアパートメントで、太陽が差し込むホールに立っていると、この地を愛する思いがよみがえってきたという。書店や劇場、夜更けの運河沿いの光景のこと――(「あの闇はとても説明できない。ベルベットに包まれるようだよ」)。

別の角度から見た寝室。17世紀後半のベネト地方の書きもの机、ムラーノ島でつくられたシャンデリア、壁には線画や水彩画が配されている。
そういうわけで夫婦はベネチアにとどまることにした。改築にはイタリア人建築家マリアンジェラ・ザンゾットを起用した。美術史家として教会や公共建築物の保全にも携わる人物だ。ワード=ジャクソンはクラシックなものを好み、50代半ばの妻はモダンなアートや家具を好むので、デザインに関する考え方は夫婦で一致していたわけではなかったが、重要な点については同意していた。内装は真面目にしすぎず、ベネチアの精神を思わせるものにしたい、と。「ついつい古めかしい雰囲気にしたくなるものだが、とても現代的に仕上げてくれた」。昨年4月、ある風の強い午後の取材の際、ワード=ジャクソンはそう語った。ザンゾットは約2年をかけて改築に取り組み、キッチンカウンターにはイストリア半島の石、壁にはマルモリーノと呼ばれる伝統的漆喰(粉末状の大理石を石灰石と混ぜる)など、イタリアゆかりの資材を揃えた。「フェイクですますのは好きじゃない」とザンゾットは言う。目指したのは「ベネチアの魂を表現すること」だ。
▼あわせて読みたいおすすめ記事